「女の子写真」は本当に「女の子」だけのもの? 長島有里枝さんが語る写真史とフェミニズムとは!?
「女の子写真」はなぜ女性性を安易にカテゴライズするのか? 写真家・長島有里枝が90年代の女性写真ムーブメントを振り返り、フェミニズムと写真表現の複雑な関係を解き明かす。男性中心的な価値観に挑む、女性の身体と表現の自由を問う力強い一冊。
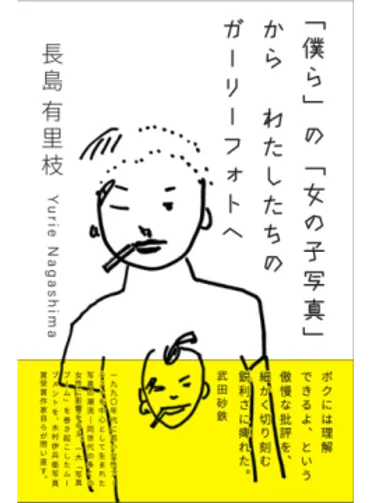
💡 1990年代の「女の子写真」ムーブメントが、女性写真家たちにとってどのような意味を持っていたのか
💡 フェミニズムの視点から「女の子写真」を再解釈することで、どのような新しい視点が得られるのか
💡 長島有里枝さんの写真作品を通して、女性の身体表現と自己表現について考える
本日は、長島有里枝さんの著作『「僕ら」の「女の子写真」からわたしたちのガーリーフォトへ』について解説してまいります。
「女の子写真」と女性作家の苦悩
女性写真家は、なぜ「女の子写真」に括られることが多いのか?
男性中心的な価値観による歪み
長島有里枝さんの著作は、写真史におけるジェンダーの偏見を浮き彫りにし、女性の表現に対する新たな視点を与えてくれると感じました。
公開日:2020/03/28
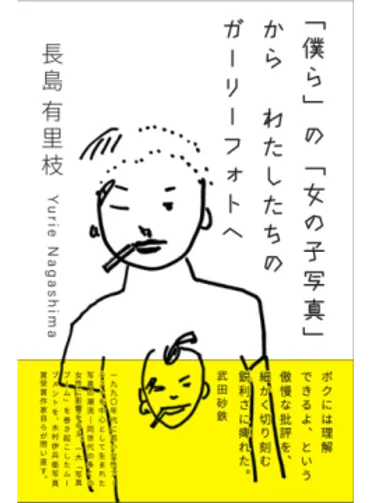
✅ 長島有里枝氏による「女の子写真」潮流の再検討を軸に、女性写真家たちが写真界や社会において不当な扱いを受けてきた現状が、資料を交えながら詳細に解説されている。
✅ 当時の評論家による「コンパクトカメラの台頭」との関連付けや、「自己中心的」「わがままで自分勝手」といった女性蔑視的な評価が、男性優位主義に基づくものだと批判している。
✅ 「女の子写真」と軽んじられてきた潮流を、女性の権利意識に鋭敏な「ガーリーフォト」という海外の概念に置き換え、新たな視点から見直すことで、その価値を再評価しようとしている。
さらに読む ⇒好書好日|Good Life With Books出典/画像元: https://book.asahi.com/article/13250690長島有里枝さんの言葉から、当時の「女の子写真」が女性蔑視的な評価に晒されていたことがよく分かります。
1990年代の「女の子写真」ムーブメントは、男性中心的な写真界において、女性写真家たちの作品が「未熟」「感性」といった言葉で安易に括られ、成熟した表現者として認められなかった状況を反映しています。
長島有里枝さんは、自身の作品が「女の子」という枠に押し込められ、技術やメッセージよりも「女の子らしさ」で語られることに疑問を抱き、作品のネガを廃棄した経験を通して、男性支配的な価値観の中で女性作家の表現がどのように歪められてきたかを訴えています。
あの時代の女性写真家たちが抱えていた苦悩が伝わってきて、胸が痛みます。
フェミニズムの視点から見た「女の子写真」
「女の子写真」はなぜ「ガーリーフォト」に?
フェミニズムとの関連性を示すため
フェミニズムの視座から「女の子写真」を分析することで、従来の認識に疑問を持つようになりました。
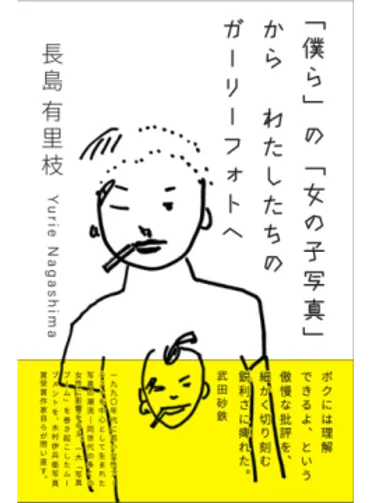
✅ 本書は、1990年代の「女の子写真」ムーブメントの中心人物であった長島有里枝が、当時の批評家や編集者による言説を批判し、このムーブメントを「ガーリーフォト」としてフェミニズムの文脈から再考するものである。
✅ 長島は当時の批評家や編集者が「女の子写真」を「直感的」「軽やか」「衝動的」などと称賛したことが、女性に対するステレオタイプに基づいた偏見であり、彼女たちを写真界の周縁に追いやったと指摘する。
✅ 本書は、写真批評におけるジェンダー・バイアスを明らかにし、フェミニズムの視座から「ガーリーフォト」を再解釈することで、過去の「女の子写真」に対する認識を問い直す。また、読者自身もジェンダー・バイアスに気づくよう促し、女性に対する認識を変えるきっかけを与える。
さらに読む ⇒IMA ONLINE出典/画像元: https://imaonline.jp/articles/bookreview/20200303yurie-nagashima/男性中心的な価値観が女性に対する評価に大きく影響を与えていたことが改めて分かりました。
長島有里枝さんの著書『「僕ら」の「女の子写真」からわたしたちのガーリーフォトへ』は、当時の批評家や編集者によって「女の子写真」と称されたムーブメントを「ガーリーフォト」と名付け直し、第3波フェミニズムとの関連性を示唆しています。
本書は、当時のメディアが「女の子写真」を「直感的」「軽やか」「衝動的」と評価した一方で、女性に対するステレオタイプを再生産していたことを批判し、女性蔑視的で差別的な評価が性差別に基づいていると主張しています。
また、フェミニズム批評が文学や美術では確立されているにもかかわらず、写真批評では性差別的な視点が採用されがちであったことを明らかにしています。
フェミニズムの視点を取り入れることの重要性を改めて認識しました。
長島有里枝さんとフェミニズム
長島有里枝さんのフェミニズムへの関心はいつから?
18歳の時です
長島有里枝さんの作品には、社会への鋭い洞察と深い人間性を感じます。
公開日:2021/05/31
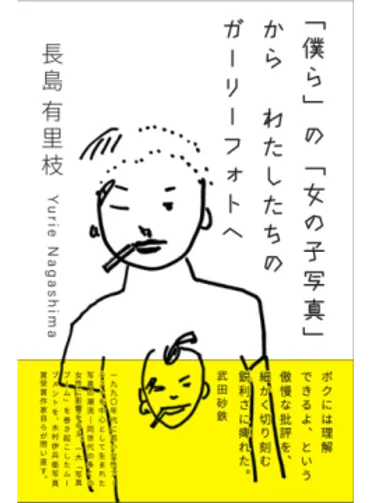
✅ 長島有里枝さんは、パートナーの母親と共同で、神戸の女性たちの思い出の詰まった古着を繋ぎ合わせてタープを制作した。この展示を通して、複雑で曖昧な女性の豊かな人生を表現している。
✅ 長島さんは、パートナーの母親との共同制作を通して、ほとんど面識のなかった相手との関係を築き、女性の創造性と技術に着目した作品を制作した。
✅ 長島さんは、女性という役割について考え、表現することで、社会とゆるやかにつながり、社会システムの構造を見直す際の指針になることを目指している。
さらに読む ⇒「雛形」違和感を観察する ライフジャーナル・マガジン出典/画像元: https://www.hinagata-mag.com/report/12561長島有里枝さんの経験を通して、女性が社会から押し付けられる役割について深く考えさせられました。
長島有里枝さんは、自身の経験を通して、女性が社会から押し付けられる「女性らしさ」や「母性」といった役割に疑問を抱き、女性が自分らしく生きるための自由を求め続けています。
18歳の時にボーヴォワールの『第二の性』を読んでフェミニズムと出会った長島さんは、自身の作品における身体表現の変化について、若い頃は外見にこだわり、摂食障害との闘いがあったが、今は身体機能の維持に関心があるという。
また、写真という視覚的なメディアにおいて、シルエットを用いることで見る人の想像力を重視するようになったことを説明し、視覚障害者の美術鑑賞体験を通して「見る」行為への執着が薄れてきているとも語っています。
長島有里枝さんの作品は、社会と個人の関係性を考える上でとても示唆に富んでいます。
セルフポートレートと女性の身体表現
長島有里枝さんの写真集は何を批判している?
女性の身体の消費
セルフポートレートを通して、女性の身体表現の新たな可能性を感じます。
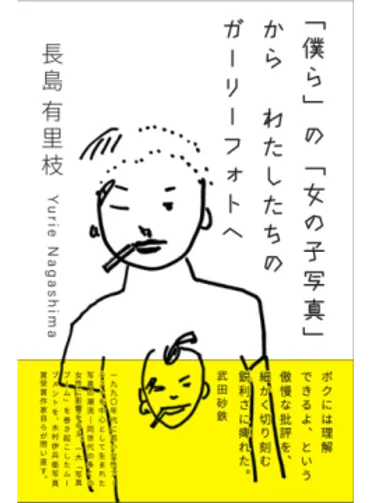
✅ 長島有里枝さんは、1990年代から写真家として活動し、「わたしの身体はわたしのもの」という主張を表現し、多くの女性たちに勇気を与えてきました。
✅ 長島さんは、1990年代に「女の子写真」と称された写真潮流に対して、フェミニズム理論に基づいた異議申し立てを行い、自身のセルフポートレート集『Self-portraits』を出版しました。
✅ 長島さんは自身が経験してきた違和感について語り、写真を通して女性が日々当たり前だと思っている違和感に気づきを与え、女性が自分の人生を見つめ直すきっかけを与えていることを示しました。
さらに読む ⇒She is シーイズ 自分らしく生きる女性を祝福するライフ&カルチャーコミュニティ出典/画像元: https://sheishere.jp/interview/202009-yurienagashima/長島有里枝さんのセルフポートレートは、男性中心的な価値観に対する抵抗の表現として、とても力強く感じます。
長島有里枝さんの写真集『Self−Portraits』は、セルフポートレートを通して、従来の写真表現における性別役割分担に対する抵抗を象徴しています。
長島さんは、当時のヘアヌードブームに対する抵抗として、女性の身体が「エロではなくアート」という言説に疑問を持ち、セルフポートレートを制作した。
女性の身体の消費を批判し、美術館に飾られる状況を作り出すことを目指していた。
また、セルフヌードの表現を通して、男性社会による搾取からの脱却、そして女性自身の「ヘアヌード」に対する痛烈な批判を表現したと述べています。
女性が自身の身体をどのように表現していくのか、改めて考える良い機会になりました。
女性たちの連帯と自己表現
「ぼくら」の「女の子写真」は女性たちの連帯を阻害した?
男性中心的な視点が原因
女性たちの連帯と自己表現の重要性を改めて認識しました。
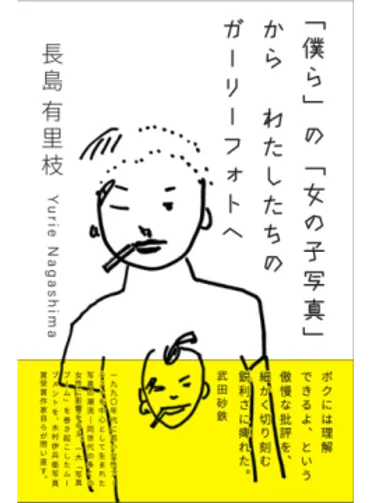
✅ この記事では、2020年1月15日発売の書籍「i-mode 2000年1月15日 ISBN:9784908465116」について解説しています。
✅ 具体的には、i-modeサービスが1990年代後半から2000年代にかけてどのように発展し、携帯電話文化に大きな影響を与えたかを説明しています。
✅ また、i-modeの登場が携帯電話の利用シーンを拡大させ、新たなコンテンツ産業を創出したことや、後のスマートフォン時代への影響について触れています。
さらに読む ⇒�G�{�i�r�@�q�ǂ��ɊG�{��I�ԂȂ�出典/画像元: https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=137314長島有里枝さんの言葉から、女性たちの連帯が社会を変える力になり得ると感じました。
長島有里枝さんの著書『「ぼくら」の「女の子写真」からわたしたちのガーリーフォトへ』は、男性中心的な視点から語られてきた「女の子写真」の言説に対して、フェミニズム理論を学んだ当事者たちが異を唱える内容です。
長島さんは、女性写真家たちの作品を「ガーリーフォト」と位置づけ、男性たちの言葉が女性たちの連帯を阻害してきた側面があると指摘します。
90年代に女性写真家の活動を当時受け止め損ねたという清水さんの経験は、当時の状況が女性たちの連帯を阻害していたことを示しています。
しかし、長島さんは、当時の女性写真家に触発された若い女性たちが、日常的にカメラを持ち歩き自己表現に取り組んでいたことを指摘し、連帯の契機は、自分がどうしたいのかという主体的な意志と深く関わっていると考えます。
女性たちの連帯が、社会を変える力になることを改めて実感しました。
本日は長島有里枝さんの著作『「僕ら」の「女の子写真」からわたしたちのガーリーフォトへ』について解説させて頂きました。
💡 1990年代の「女の子写真」は、女性写真家たちの表現が軽視され、男性中心的な価値観によって歪められていた.
💡 フェミニズムの視点は、写真批評におけるジェンダー・バイアスを明らかにし、女性の表現を再評価する
💡 長島有里枝さんの作品は、女性の身体表現と自己表現について考えるきっかけを与えてくれる.


