ストップいじめ!ナビ:荻上チキさんが提唱するいじめ解決策とは?いじめ問題の根深い原因を徹底解剖!!
いじめ問題解決へ!ジャーナリスト荻上チキ氏が設立した「ストップいじめ!ナビ」。学術的根拠に基づいた対策で、いじめ撲滅を目指します。学校、家庭、社会全体でいじめをなくすために、今すぐできることを知りませんか?
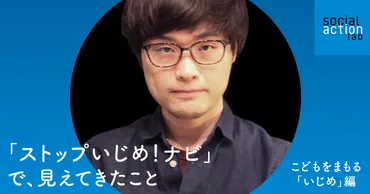
💡 いじめ問題の解決に向けた具体的な対策を提示している。
💡 子どもの目線に立った対策を提案している。
💡 いじめ問題に関する学術的な情報を社会に共有し、客観的な議論を促進している。
それでは、ストップいじめ!ナビの活動内容について詳しく見ていきましょう。
ストップいじめ!ナビの設立と初期の活動
ストップいじめ!ナビ設立のきっかけは?
中学生いじめ自殺事件
はい、ストップいじめ!ナビは、いじめ問題の解決に向けて、様々な活動を行っているのですね。
公開日:2022/06/24
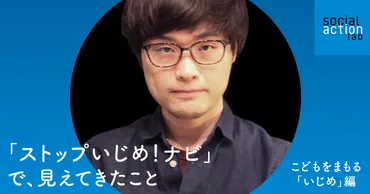
✅ 「ストップいじめ!ナビ」は、いじめ問題の解決に向けた具体的な対策を提示するため、データに基づいた解決方法や子どもの目線に立った対策を提案している。
✅ 記事では、いじめの発見方法として、子どもの言動や態度、身体的な変化に注意することや、いじめられたことを記録しておくことの重要性を強調している。
✅ いじめ防止対策推進法の施行に伴い、学校現場でもいじめ問題に対する取り組みが進められているが、ブラック校則など、いじめを助長する要因も存在しており、課題が残されている。
さらに読む ⇒ソーシャルアクションラボ | 毎日新聞 -出典/画像元: https://socialaction.mainichi.jp/2018/08/23/972.htmlいじめ問題は深刻な問題であり、学校現場でも対策が進められている一方で、課題も残っていると感じます。
2011年、大津市の中学生いじめ自殺事件をきっかけに、荻上チキさんは、社会問題として大きく取り上げられる中で、政治家やコメンテーターによる科学的根拠に乏しい発言が多く見られたことに危機感を覚え、ストップいじめ!ナビを設立しました。
ストップいじめ!ナビは、いじめに関する学術的な情報を社会に共有し、より客観的な議論を促進することを目的としています。
設立当初は、社会応援ネットワーク全国の小中学生向けの『子ども応援便り』編集室を母体として活動を開始しました。
その後、東日本大震災以降は、被災地向けの「心のケア」の出張授業や全国の小学校への『防災手帳』無料配布、コロナ禍における「こころの健康サポート部」サイト運営など、学校現場からの声に寄り添う活動に力を入れてきました。
私も、いじめ問題については、もっと深く知りたいと思っていました。今回の記事で、具体的な対策を知ることができて嬉しいです。ありがとうございます。
荻上チキさんの経験と学校教育への提言
いじめ対策で荻上チキさんが提言するのは?
相談窓口設置や教員増員など
はい、荻上チキさんの経験に基づいた提言はとても興味深いですね。
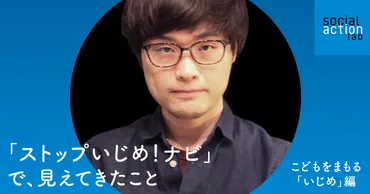
✅ 荻上チキさんは、いじめやブラック校則についての著書を通して、学校を子どもたちが理不尽に耐える場所ではなく、安心できる場所に変えようと活動しています。
✅ 荻上さんは、いじめは夏休み明けや6月に増える傾向があり、学校での権力関係が形成される過程で発生すると分析しています。また、多忙な教員や学校における管理主義的な風潮が問題だと指摘し、スクールロイヤーの配置や道徳の教科化の無意味さを訴えています。
✅ 荻上さんは、理不尽な校則が子どもたちの精神的な負担になっている現状を指摘し、学校は理不尽に抵抗するスキルを身につける場であるべきだと主張しています。自身の経験を通して、子どもへの理不尽な指導は「脳への暴力」であり、うつ病などの精神的な問題につながる可能性があると訴えています。
さらに読む ⇒東京すくすく | 子育て世代がつながる ― 東京新聞出典/画像元: https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/education/17147/荻上チキさんの経験を通して、学校教育の現状における課題が浮き彫りになりました。
荻上チキさんは、自身もいじめやブラック校則の被害者であり、その経験から学校教育の改善を訴えています。
いじめ対策として、自身が行った大規模調査の結果に基づき、夏休み明けや6月がいじめのピークであることを明らかにし、LINEなどのアプリを通じた相談窓口の設置、教員の人員増、スクールロイヤーの配置などを提言しています。
また、ブラック校則については、生徒や保護者に対する調査で、多くの学校で細かい規則による管理主義化が進んでいる実態を明らかにし、校則の改善が生きづらい社会を変えることにつながると考えています。
さらに、自身のうつ病をオープンにすることで、子どもへの理不尽な指導は脳への暴力であり、自尊心を傷つけるという経験に基づいたメッセージを発信しています。
私は、学校教育の改善には、子どもの意見をもっと反映させる必要があると感じています。
ストップいじめ!ナビの活動内容と目的
いじめ問題解決のため、ストップいじめ!ナビは何に取り組んでいますか?
調査研究、対策立案、啓発活動など
はい、いじめや嫌がらせから抜け出す方法はいくつかあるんですね。
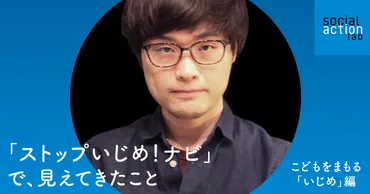
✅ いじめや嫌がらせから抜け出す方法は、相談窓口への連絡、記録、他者の経験からの学び、弁護士や警察への相談など、いくつかの方法があります。
✅ 相談窓口としては、チャットや電話での相談窓口が紹介されており、チャイルドライン、いきづらびっとなどの相談窓口の連絡先が掲載されています。
✅ 相談する前に、いじめ攻略アイテム集を活用し、伝えたいことをまとめておくと良いとされています。また、不安なときは家族や先生に相談したり、チャイルドラインに連絡したり、自分の気持ちをメモに書き留めておくことも有効とされています。
さらに読む ⇒子どものいじめに役立つ脱出策出典/画像元: https://stopijime.jp/相談窓口の存在は心強いですね。
ストップいじめ!ナビは、いじめ問題に関する調査研究、対策立案、提言・啓発活動、情報発信などを行い、いじめ問題の改善・解決に向けた社会的基盤整備を目的としています。
主な事業は、情報発信を目的としたウェブサイト運営、具体的な対策および相談窓口の提供、いじめ問題に関する正確な情報の啓蒙活動などです。
2014年からは団体サイトをオープンし、より積極的に情報発信を行っています。
また、2015年からは弁護士チームによる学校いじめ予防授業を開始し、2017年には授業回数が100回を突破しました。
近年は、SNSを活用した情報発信や、関係機関との連携強化にも力を入れています。
活動資金は、寄付によって支えられており、いただいた寄付は、活動の広報、調査研究、政策提言、事務所維持費などに活用されます。
私も、何か困ったことがあったら、相談できる窓口があれば安心できます。
ストップいじめ!ナビの具体的な活動と情報提供
いじめ問題解決のため、ストップいじめ!ナビではどんな取り組みをしていますか?
多角的な対策と連携を推進
なるほど、いじめは必ずしも増加しているわけではないんですね。
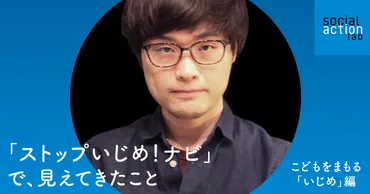
✅ 記事では、いじめ問題に関する統計データに基づいて、いじめは必ずしも増加しているわけではないことを指摘しています。
✅ 文部科学省の統計データは、定義の変更や学校側の認知度によって数値が変動し、実際のいじめ発生件数とは一致しない可能性があることを説明しています。
✅ 一方で、教育政策研究所の統計では、いじめ被害に関する具体的な内容(仲間はずれ、無視、陰口など)について生徒本人に聞き取り調査を行っており、文部科学省のデータとは異なる視点からいじめの実態を把握しています。
さらに読む ⇒SYNODOS – 専門家の解説と教養のポータルサイト出典/画像元: https://synodos.jp/opinion/education/525/具体的な対策と情報提供によって、いじめ問題の解決に貢献しているんですね。
ストップいじめ!ナビでは、ジャーナリスト、弁護士など専門家が集結し、いじめ問題のデータに基づいた解決策を、子どもの目線に立った具体的な対策とともに提供しています。
サイトでは、相談機関へのアクセス方法や、いじめ防止対策推進法の実効性に関する提言なども掲載されており、いじめ問題の解決に向けて多角的なアプローチを行っています。
荻上さんは、メディアのセンセーショナルな報道ではなく、具体的な対策を重視し、学校・保護者・行政・メディアの連携によるいじめ問題の解決を訴えています。
記事では、いじめに関する統計、いじめの背景にあるブラック校則、家庭におけるいじめ発見チェックシートなどが紹介されています。
荻上さんは、親は子どもの状態を常に見て、信頼関係を築き、話しやすい環境を作ることを強調しています。
また、子どもには、いじめられたことを記録しておくことを推奨しています。
記録は、証拠となるだけでなく、気持ちを整理し、対策を立てる上で役立ちます。
いじめ問題は、学校だけでなく、家庭でも意識する必要があると感じました。
荻上チキさんの講演とストップいじめ!ナビの情報発信
荻上チキさんはどんな講演をしたの?
先生向けいじめ対策
荻上チキさんの講演は、いじめ問題への理解を深める上でとても有益だったと思います。
公開日:2019/04/01
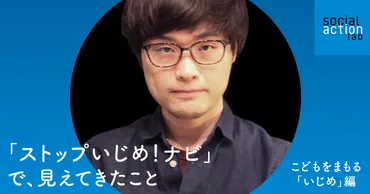
✅ NPO法人「ストップいじめ!ナビ」は、2011年の大津市中2いじめ自殺事件をきっかけに、評論家の荻上チキさんによって設立されました。
✅ 主な活動内容は、いじめに関する学術的な情報を社会に発信すること、学校に出向いていじめ対策の授業を行うこと、法整備に向けたロビー活動を行うことです。
✅ 設立の背景には、いじめに関する実証的研究が社会に共有されていないことや、政治家による科学的根拠に乏しい発言、いじめ対策に対する法整備のイメージのずれなどが挙げられます。
さらに読む ⇒寺子屋朝日│すべての人の「学び」を応援する出典/画像元: https://terakoya.asahi.com/article/15321160ストップいじめ!ナビは、様々な活動を通して、いじめ問題の解決を目指しているんですね。
荻上チキさんは、寺子屋朝日forTeachersで、先生向けのいじめ対策について講演を行いました。
講演では、いじめの現状、国の調査研究の課題、ネットいじめ、いじめ体験の影響、いじめ予防プログラム、学校環境づくりなど、幅広いテーマについて触れられています。
ストップいじめ!ナビは、ウェブサイトやメディアを通じて、いじめに関する情報を発信し続けています。
私も、積極的に情報発信し、いじめ問題解決に貢献したいです。
ストップいじめ!ナビは、いじめ問題の根深い原因を分析し、学術的な視点から解決策を提案していることが分かりました。
💡 いじめ問題の解決には、学校、家庭、社会全体で取り組む必要がある。
💡 具体的な対策と情報提供を通して、いじめ問題の解決に貢献している。
💡 子どもたちの安全な学校環境づくりのために、今後も積極的に活動していく。


