新井紀子氏が警鐘を鳴らす!AI時代を生き抜くために必要な「読解力」とは?AI時代の読解力、教育の重要性、東ロボくんプロジェクト、そして未来への提言
AI時代の羅針盤!新井紀子氏が警鐘を鳴らす、読解力の重要性。AIは万能ではない!その限界を理解し、AIを使いこなすために必要なのは、゛正しく読む力゛、つまり汎用的読解力だ。AIvs.人間、生き残る術は?東ロボくんプロジェクトから見えた、教育の未来、そして幼児期の体験が生み出す、人間ならではの強みとは?変化の激しい時代を生き抜くためのヒントがここに!
東ロボくんプロジェクトとAIの可能性
AIは東大に合格できる?東ロボくんプロジェクトの目的は?
AI能力と教育のあり方を模索するため。
AI研究プロジェクト「東ロボくん」を通して見えてきたAIの可能性と限界について解説します。
AIとの共存社会で、私たちがどのように学び、成長していくべきかを探ります。
公開日:2022/07/14

✅ AI研究プロジェクト「東ロボくん」は東大合格を目指したが、理科や図の理解で困難をきたし、人間の゛常識゛やイラスト理解がAIの苦手分野であることが判明。
✅ AIは特定のデータ処理や作業において人間より優れているため、一部の仕事はAIに代替される可能性があるものの、未来を予測するのは困難であり、変化に対応できる学び直す力(リスキリング)が重要。
✅ リスキリングはテキストを通して行われるため、情報を読み解き、質問する力を身につけることが、変化の激しい時代を生き抜くために不可欠。
さらに読む ⇒人工知能は東大に合格できる?AI時代を楽しむヒント\東ロボくん/出典/画像元: https://aritorism.com/archives/2853東ロボくんプロジェクトを通して、AIの限界と可能性が浮き彫りになったのは興味深いですね。
AI時代には、変化に対応できる力が重要だと感じました。
新井紀子氏は、AIと人間の能力の違いを研究するため、東大入試に挑戦するAI「東ロボくん」プロジェクトを開始しました。
このプロジェクトは、AI技術の進歩により、単純作業だけでなく、高度な仕事も代替される可能性があり、多くの人が新しい仕事を見つけられるとは限らないという問題意識に基づいています。
東ロボくんは、選択式の全国共通試験と記述式の二次試験で構成される東京大学の入試突破を目指し、キーワード検索と最適化の能力を駆使して問題を解きます。
このプロジェクトを通じて、AIの現在の動作原理と限界を理解し、AI時代の教育のあり方を探求しています。
AIが東大に挑戦したプロジェクト、面白いですね! AIが得意なこと、苦手なことがわかるのは、今後の創作活動にも役立ちそうです。
AI時代を生き抜くための知恵
AI時代に必須の力とは?読解力、それとも?
主体的な知恵、非認知能力、読解力です。
AI時代を生き抜くための具体的な知恵と、読解力を高める方法について説明します。
主体的な学びを促すには何が必要なのか、詳しく見ていきましょう。
公開日:2019/04/01

✅ AI時代には、既存の正解を出す力よりも、新たな問いを立てる力が重要であり、そのためには、切実でリアリティのある問いを持つことが大切である。
✅ AI時代に役立つ力として、どのような分野でも主体的に自学自習できる能力が重要であり、その基盤となるのが汎用的な読解力と学習言語の習得である。
✅ 子どもの読解力を高めるためには、各科目での音読が効果的であり、つまずきを把握することにもつながる。小学校から高校にかけて読解力を高めることが、その後の学びをスムーズにする。
さらに読む ⇒寺子屋朝日│すべての人の「学び」を応援する出典/画像元: https://terakoya.asahi.com/article/15087325AI時代には、多様な能力が求められることがよくわかりました。
主体的な知恵を磨き、変化に対応できる読解力を身につけることが重要ですね。
新井紀子氏とSAPIXYOZEMIGROUPの髙宮敏郎氏の対談では、AI時代における教育の重要性が議論されました。
新井氏は、AIの能力向上に驚きを示し、知的労働の効率化と雇用への影響を懸念。
AI時代に人間が生き残るためには、知識量ではなく、身体的な体験を通じた主体的な知恵、非認知能力、読解力が重要だと指摘しました。
5歳までの幼児教育における原体験、具体的には、喧嘩や遊び、喜びや悔しさを通して培われる能力が、AIにはない人間ならではの強みになると強調。
髙宮氏も、AIが入り込めない幼児期の体験の重要性を支持し、読解力の重要性を強調しました。
AIが言葉を流暢に操れても、意味を理解しているわけではないため、人間はAIが出した結果を理解し、意思決定や問題解決を行う能力が重要であり、図書館の利用や対話、協調性やリーダーシップも重要であると述べました。
そして、小学校から大学までの教育は、学び方を学ぶ場であり、自学自習できる汎用的な読解力を身につけることが、変化の激しい時代を生き抜くために不可欠であると結論づけました。
AI時代を生き抜くために、読解力や主体的な知恵が大切なんですね。色々な経験をして、自分も成長したいと思いました。
AIに関する書籍と新聞記事
AIは万能?新井紀子氏が警鐘を鳴らす内容は?
AIの能力は計算に限定、シンギュラリティを否定。
新井紀子氏の書籍や記事を通して、AI時代における読解力の重要性をさらに深く掘り下げます。
未来を見据えた読書とは何か、考えていきましょう。
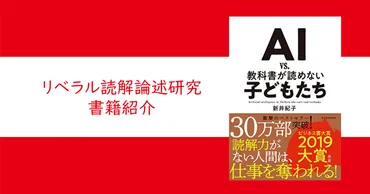
✅ 本書は、AIの情報処理の限界を指摘し、AIが「意味」を理解できないため、将来的にシンギュラリティがすぐに実現する可能性を否定しています。
✅ 著者は、中高生の読解力調査の結果をもとに、AIと人間の読解力に大きな差がない可能性を示唆し、AI時代における人間の「最悪のシナリオ」とその対策について考察を促しています。
✅ AI技術の発展が進む社会で、人間にとって必要となる「意味」の理解に基づく柔軟な判断力を養うことの重要性を説き、将来を見据えた読書を推奨しています。
さらに読む ⇒大学受験 Y-SAPIX出典/画像元: https://y-sapix.net/n/ne6044fe92029AIに関する書籍や記事を通して、AIに対する理解を深めることが大切だと感じました。
未来を生き抜くために、読書を習慣にしたいですね。
新井紀子氏の書籍『AIvs.教科書が読めない子どもたち』は、AI万能論に対する警鐘を鳴らす古典として位置づけられます。
この書籍では、AIは計算機であり、その能力は四則演算と数学的言語に限定されると指摘し、シンギュラリティ(技術的特異点)の到来を否定しています。
また、朝日新聞に掲載された記事では、対話型AI「ChatGPT」を子どもに使わせるべきかという問題について、メリットとデメリットを踏まえ、特に10代の子どもを持つ親が悩む問題に焦点を当てています。
新井氏は、東大合格を目指すAI「東ロボくん」プロジェクトを主導した経験から、ChatGPT利用に関する結論を提示しています。
AIに関する書籍を読んで、AIについてもっと詳しく知りたいと思いました。AIが苦手な部分を補えるように、読解力を高めたいです。
新井紀子氏の提言は、AI時代を生き抜くための羅針盤となるでしょう。
読解力を高め、主体的に学び続けることが大切ですね。
💡 AI時代には、読解力、主体的な学びが重要である。
💡 東ロボくんプロジェクトを通して、AIの限界と可能性が示された。
💡 AI時代を生き抜くには、未来を見据えた読書が不可欠である。


