発達障害支援の今後は?学校教育、合理的配慮、進路選択まで徹底解説!(発達障害支援法)発達障害支援の最新情報:学校教育と合理的配慮、進路選択のポイント
発達障害への理解と支援が世界で加速!法改正、学校教育の変化、合理的配慮の義務化、教員研修など、包括的な支援体制が構築されています。進路選択から卒業後のサポートまで、保護者や関係者の役割も重要です。 インクルーシブ教育実現に向けた課題と対策とは?
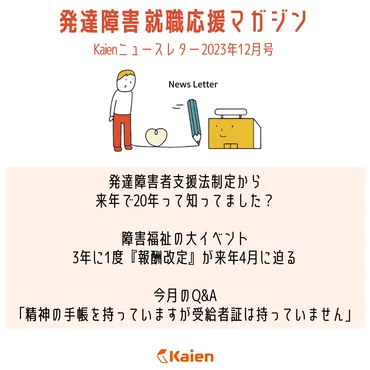
💡 発達障害者支援法の改正や国際的な動向、障害者雇用支援の最新情報について解説します。
💡 学校教育における合理的配慮の提供、教員の専門性向上、支援体制の強化について解説します。
💡 進路選択、卒業後の生活における支援、保護者の役割について解説します。
それでは、まず発達障害支援の国際的な進展について見ていきましょう。
発達障害支援の国際的な進展
発達障害支援、日本と中国でどんな変化があった?
法整備、教育、生活支援が進んでいます。
発達障害者支援の国際的な進展について解説します。
公開日:2024/02/20
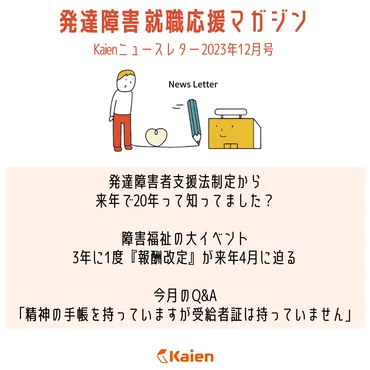
✅ 障害者雇用に特化した就職・転職サイト「マイナーリーグ」が、EY Japan DAC、LINEヤフー株式会社、株式会社イルカなどの求人を紹介しています。
✅ 2024年は発達障害者支援法制定20周年を記念し、Kaienが様々なイベントを開催。正月には生放送で過去20年を振り返る特集、5月と9月にもイベントを予定しています。
✅ 障害福祉サービスの報酬改定が2024年4月に迫っており、Kaienが動画でその内容を解説。メディア掲載情報も提供しています。
さらに読む ⇒株式会社発達障害の方のための就労移行支援・自立訓練・ニューロダイバーシティ社会実現を推進出典/画像元: https://www.kaien-lab.com/newsletter/202312nl/日本だけでなく、中国でも法整備が進んでいることに驚きました。
20周年記念のイベントも開催されるようで、今後の支援に期待できます。
近年、発達障害に対する理解と支援は世界的に進み、法整備も進んでいます。
2005年に発達障害者支援法が施行され、2016年には改正が行われ、切れ目のない支援体制が構築されました。
中国でも、2006年の義務教育法改正により自閉症児が義務教育の対象となり、権利保障の動きが進んでいます。
2017年には特別支援学校の設置推進や、低所得障害者への生活補助、重度障害者への介護補助制度も設けられました。
これらの取り組みは、1991年から始まった5ヶ年計画に基づき、具体化されています。
発達障害支援に関する法整備が国際的に進んでいるんですね。中国の事例も興味深いです。日本も、もっと支援体制が整うと良いですね。
学校教育における発達障害児への支援
特別支援教育、現場の課題と、文科省の対策は?
教員不足の中、支援体制強化が急務。
学校教育における発達障害児への支援について解説します。
公開日:2019/04/01
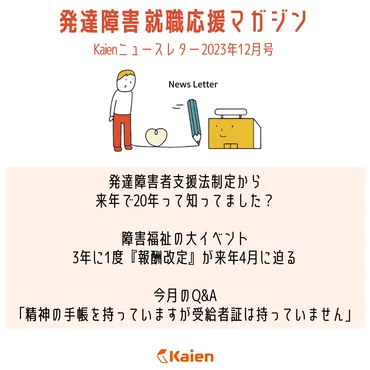
✅ 学校教育では、障がい者差別解消法に基づき、合理的配慮の提供が重要であり、教員をはじめとする教育関係者はその内容を理解する必要がある。
✅ 合理的配慮とは、障がいのある人からの要請に応じて、社会の障壁を調整することであり、条約や法律で義務付けられている。2024年4月からは事業者も合理的配慮の提供が法的義務となる。
✅ 合理的配慮は、「必要かつ適当な配慮」と「過重な負担でない」ことが重要であり、障がいの捉え方が医学モデルから社会モデルへと変化したこと、配慮しないことが差別につながるという認識が広まったことが背景にある。
さらに読む ⇒寺子屋朝日│すべての人の「学び」を応援する出典/画像元: https://terakoya.asahi.com/article/15007874合理的配慮の法的義務化は重要ですね。
教員の人手不足という課題もあるようですが、外部との連携など、様々な対策が取られているのは心強いです。
学校教育の現場では、2007年度から特別支援教育が全学校で実施され、2017年度からは通級指導の教員が基礎定数化されるなど、大きな転換期を迎えました。
学習指導要領では、個別の教育支援計画や指導計画の策定が定められています。
2016年の障害者差別解消法により、学校での合理的配慮が義務化されましたが、教員の人手不足という課題も抱えています。
文部科学省は、特別支援コーディネーターの配置、校内委員会開催、外部専門家との連携などを推奨し、支援体制の強化を図っています。
2022年の文部科学省調査によると、通常学級における特別な配慮を必要とする子どもの割合は約8.8%と増加傾向にあり、より丁寧な支援が求められています。
合理的配慮の提供が義務化されることで、学校現場でのサポートがより充実することを期待します。教員の方々の負担も考慮してほしいですね。
通常学級における合理的配慮と保護者の役割
発達障害児への学校の配慮、法的に義務って本当?
学校教育法に基づき、法的義務です。
通常学級における合理的配慮と保護者の役割について解説します。
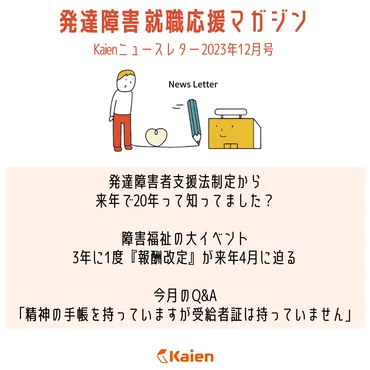
✅ 合理的配慮とは、障がいや特性による困りごとを抱える人が、教育や社会生活において平等に参加できるよう、負担が重すぎない範囲で個別のニーズに対応すること。
✅ 2016年4月から行政機関で義務化され、2024年4月からは塾や習い事などの事業者でも合理的配慮の提供が義務化される。
✅ 合理的配慮の具体例として、視覚障害への座席配慮、聴覚障害への座席配置、知的障害への教材活用、肢体不自由への補助具使用などがあり、学校や事業者での事例が紹介されている。
さらに読む ⇒ファミケア疾患児・障がい児家族の毎日を楽しく出典/画像元: https://famicare.jp/2023/12/16/reasonable-accommodation/合理的配慮の具体例が分かりやすく説明されていて参考になりますね。
保護者が学校と連携し、子どもの特性に合わせた支援を求めることが大切だと感じました。
発達障害のある児童が小中学校の普通学級に通う場合、学校は発達障害への配慮をする法的義務があります。
これは学校教育法第81条に基づき、学習面だけでなく生活面においても支援を行う必要があると定められているためです。
合理的配慮とは、子どもの特性に応じた柔軟な対応を行い、学びの障壁を取り除くことで、学習環境の調整や、カスタマイズされた学習内容、感情のコントロール支援、ソーシャルスキルのトレーニングなどが実践例として挙げられます。
しかし、過去の価値観や法律の知識不足から、一部の教員が通常の学級での発達障害への配慮を否定することがあり、保護者は学校長や教育委員会への相談など、様々な対処法を取ることができます。
合理的配慮の具体的な例を知ることができて、とても勉強になりました。子どものために、親としてできることをもっと学びたいです。
教員の専門性向上と支援体制の強化
インクルーシブ教育成功の鍵は?教員の何が重要?
教員の専門知識・技能の向上が不可欠!
教員の専門性向上と支援体制の強化について解説します。
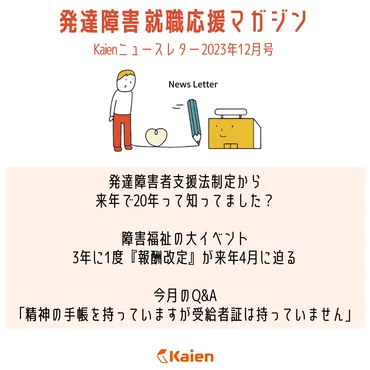
✅ あるイベントに関する記事であり、イベントの目的や内容、参加方法などが説明されている。
✅ イベントでは様々な企画が行われ、参加者同士の交流や、特定の分野に関する知識の習得を促すような内容が含まれている。
✅ 記事は、参加者だけでなく、イベント開催に関わる人々にも呼びかけ、イベントを成功させるための協力を呼びかけている。
さらに読む ⇒特別支援教育の実践情報年月号「合理的配慮」がみえる!個別の支援計画・指導計画づくり出典/画像元: https://www.meijitosho.co.jp/detail/26164教員の専門性向上が不可欠ですね。
研修だけでなく、外部人材の活用や、特別支援学級の教員の専門性向上も重要だと感じました。
インクルーシブ教育システムを構築するため、全ての教員が特別支援教育に関する基礎的な知識・技能を持つことが不可欠です。
教員養成段階での習得が理想ですが、現職教員に対しては研修等による知識・技能の向上が求められます。
専門性の確保には外部人材の活用も必要です。
特別支援学級や通級指導の担当教員の専門性は重要であり、研修を通じて専門性を高める必要があります。
また、特別支援学校教員の免許取得率向上、専門性担保のため養成・採用段階での配慮が必要であり、現職教員への研修も促進します。
教員の指導力向上が必要であり、合理的配慮の理解を深め、障害種別の担当教員を育成することも重要です。
教員の専門性向上が、インクルーシブ教育の鍵となるんですね。教員の方々には、ぜひ専門性を高めて、子どもたちを支えてほしいです。
進路選択と卒業後の生活
発達特性のある子の高校卒業後、一番大切なことは何ですか?
特性に合った進路選択と、卒業後のサポート。
進路選択と卒業後の生活について解説します。
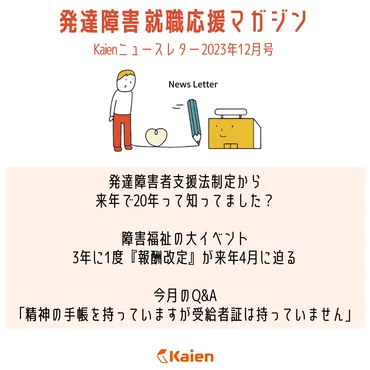
✅ 発達障害のある高校生の卒業後の進路は、「進学」「働く」「働く準備」の3つに大別され、それぞれの選択肢に応じた準備と情報収集が必要。
✅ 進路選択のためには、自分の希望、得意なこと、周囲からの期待を整理し、スケジュールを立てて準備することが重要。
✅ 進学の場合は合理的配慮について、就労の場合は働き方について、それぞれ相談できる窓口や支援機関を活用することが望ましい。
さらに読む ⇒学研キッズネット出典/画像元: https://kids.gakken.co.jp/teacher/tokushi/zukai_03/進路選択の準備や、卒業後のサポートについて、具体的に説明されていて参考になります。
親として、子どもの自立を促しつつ、サポートしていくことが大切ですね。
発達障害や特性のある子の高校卒業後の進路は多岐にわたり、大学進学、専門学校進学、就職など様々な選択肢があります。
進学した場合は、大学のサポート体制や、ハローワーク、高等職業訓練校などの活用も有効です。
親は子どもの自立を促しつつ、相談相手となり、失敗から学ぶ機会を与えることが大切です。
各家庭で子どもの特性に合わせた進路選択や、進学・就職後のサポートの重要性が示唆されています。
卒業後の生活においては、学生相談室の活用や医療機関との連携も重要になります。
卒業後の進路について、様々な選択肢があることが分かり、安心しました。子どもとよく話し合い、一緒に進路を考えていきたいです。
本日の記事では、発達障害支援に関する様々な情報をお届けしました。
今後の支援体制の発展に期待し、私たちも正しい知識を身につけていくことが大切ですね。
💡 発達障害支援は、国際的な法整備と、学校教育での合理的配慮の提供が重要です。
💡 教員の専門性向上と、保護者の積極的な関わりが、子どもたちの成長を支えます。
💡 卒業後の進路選択においては、本人の希望と、適切なサポートが不可欠です。


