AI時代を生き抜く保育とは?汐見稔幸先生が語る保育の未来とは?汐見稔幸先生が語る、AI時代を生き抜くための保育のヒント
AI時代を生き抜く子どもたちのために、保育の質を向上させよう! 汐見稔幸氏が語る、成長・楽しさ・幸せを育む保育の秘訣とは? 「子ども主体」の保育の本質、本物の文化との出会い、子どもの権利条約に基づく保育の実践例を解説。保育者が子どもたちの「やりたい!」を引き出し、主体性と創造性を育む方法を、具体的な事例を通して紹介。明日からの保育に活かせるヒントが満載です!
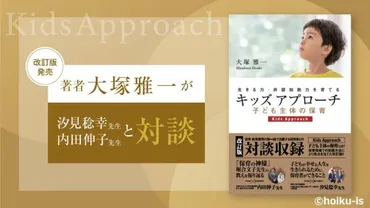
💡 AI時代に必要とされる、子どもたちが主体的に生きる力を育む保育の重要性を解説します。
💡 子どもたちの「やりたい!」を引き出す環境作り、そして成長を促す経験の重要性について解説します。
💡 豊かな人間関係を築き、共感性を育むことの重要性について解説します。
それでは、汐見稔幸先生の提唱する保育の重要ポイントを3つご紹介します。
AI社会を生き抜く力:保育の新たな使命
AI時代に不可欠な3要素とは?保育士の役割は?
成長・楽しさ・幸せを育むこと。子供の主体性を育む。
幼児教育の父・倉橋惣三先生の理論を基にした、子ども主体の保育メソッド「キッズアプローチ」についてご紹介します。
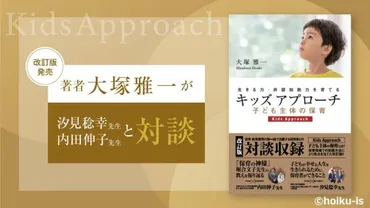
✅ 「キッズアプローチ」は、幼児教育の父・倉橋惣三先生の理論と、堀合文子先生の指導を受けた大塚雅一先生が提唱する、子ども主体の保育メソッドです。
✅ 改訂版では、汐見稔幸先生との対談で「子どもが幸せに生きるために保育者ができること」について、また内田伸子先生との対談で堀合文子先生から学んだ保育について語られています。
✅ 書籍では、保育者向けに、子どもの心に響く言葉や伝え方、子どもが思考を働かせるための環境づくりなど、実践的なノウハウが紹介されています。
さらに読む ⇒1日3分で保育を楽しく|保育士・幼稚園教諭のための情報メディア【ほいくis/ほいくいず】出典/画像元: https://hoiku-is.jp/article/detail/1054/子どもたちの内面から意欲を引き出し、成長を促す保育の重要性がよくわかりました。
AI時代に必要な力を育む環境作りのヒントが詰まっていますね。
2018年の保育所保育指針改定と2020年からの教育改革を受け、保育の質向上を目指す保育者に向けて、汐見稔幸氏は重要なメッセージを発信しています。
AI社会において人間が幸せに生きるために不可欠なのは、機械が代替できない3つの要素を育むこと、つまり「体で覚えていくこと(成長)」「アイデアを出し合うこと(楽しさ)」「豊かな人間関係を作ること(幸せ)」です。
保育者の仕事は、これらの要素を重視し、子どもの成長を促す環境を作ること、すなわち『人間の幸せ』を考えることにあります。
具体的には、子どもが「やりたい!」という意欲を引き出す環境作り、成長を実感できる経験、仲間との協調性や共感を育むことが重要です。
子どもたちが主体的に生き、物事を面白がる力を育むために、保育者はその基盤を築く役割を担っています。
AI時代に、人間が幸せに生きるために必要な要素を保育で育むという考え方に大変感銘を受けました。具体的に子どもたちの主体性を育む方法を知りたいです。
「子ども主体」という言葉の真意
7割の保育者が推進!「子ども主体」保育の課題は?
放任との誤解、線引きの悩み。
汐見稔幸先生がオンライン講座で解説する、保育における「主体性」の本質についてご紹介します。
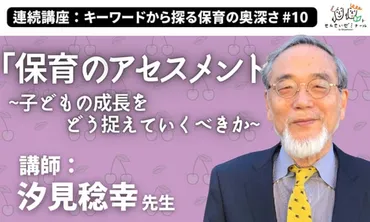
✅ 汐見稔幸先生によるオンライン講座で、保育における「主体性」の本質を理解することを目的としている。
✅ 幼稚園教育要領や保育所保育指針における「主体」という言葉の使われ方や、歴史的な背景にある哲学的議論を解説し、保育現場での主体性の育み方を学ぶ。
✅ 「主体性」という言葉の重要性、関連概念、保育者の役割、これからの時代に求められる意義について、汐見先生の講演を通して深く理解できる。
さらに読む ⇒みんなの幼児と保育出典/画像元: https://hoiku.sho.jp/movie/186252/「子ども主体」の保育の真意を理解し、現場で実践するためのヒントが満載ですね。
「放任」との違いを明確にすることが重要という点も印象的でした。
近年、多くの保育園で「子ども主体」の保育が推進されています。
しかし、その実践には様々な疑問や課題が伴っています。
汐見稔幸先生は、保育者向けのオンライン研修『子ども主体の保育をどのように具体化していくか~特に発達過程、環境による保育に注目して~』で、現代の保育と以前の保育の違い、真の「子ども主体の保育」で大切なこと、現場での実践方法について解説しました。
Instagramのアンケート調査では、約7割の保育者が「子ども主体」の保育を推進しているまたは、推進しようとしていると回答しました。
汐見先生は、この結果に対し、保育指針策定に関わった経験から「ようやく7割まで来た」という思いを語っています。
一方で、「子ども主体」の保育が「放任」と誤解されやすい現状や、子ども主体と放任の線引きに悩む保育者が多いことについても言及し、その違いを正しく理解していくことの重要性を指摘しました。
「子ども主体」という言葉の理解が深まりました。実践する上での課題や、その解決策について、もっと詳しく知りたいです。
次のページを読む ⇒
汐見稔幸氏が語る、保育における「本物の文化」との出会い。子どもの主体性を育む環境づくりと、保育者の役割とは?AI時代を生き抜く力を育むヒントがここに。

