AI時代を生き抜く保育とは?汐見稔幸先生が語る保育の未来とは?汐見稔幸先生が語る、AI時代を生き抜くための保育のヒント
AI時代を生き抜く子どもたちのために、保育の質を向上させよう! 汐見稔幸氏が語る、成長・楽しさ・幸せを育む保育の秘訣とは? 「子ども主体」の保育の本質、本物の文化との出会い、子どもの権利条約に基づく保育の実践例を解説。保育者が子どもたちの「やりたい!」を引き出し、主体性と創造性を育む方法を、具体的な事例を通して紹介。明日からの保育に活かせるヒントが満載です!
文化との出会いを促す:保育環境のヒント
保育で大切な「本物の文化」との出会いとは?
子どもの「作りたい」を刺激する環境!
汐見稔幸先生の講演を基に、保育における文化との出会いを促す環境作りについてご紹介します。
公開日:2022/01/28
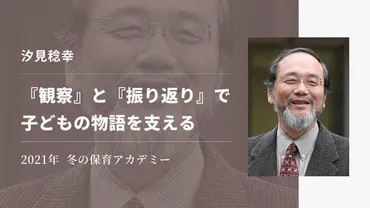
✅ 『冬の保育アカデミー』での汐見稔幸先生の講演内容を基に、保育における教育の意味を再考し、特に幼児期教育の重要性を強調している。
✅ 幼児期の教育の柱として、自己愛を育むことと、他者への共感力を高めることの重要性を説き、ルソーの思想を引用して説明している。
✅ 子どもの主体性を引き出すために、遊びへの没頭を促し、大人が適切なアドバイスやヒントを与えることの重要性を、自身の経験を通して語っている。
さらに読む ⇒手ぶら登園|おむつを保育施設に直接お届けする定額制サービス出典/画像元: https://tebura-touen.com/column/archives/3273子どもたちが本物の文化に触れ、心を動かす経験を提供することの重要性がよく分かりました。
保育者の役割の大きさを改めて感じます。
汐見稔幸氏は、保育における「本物の文化」との出会いの重要性を強調しています。
子どもたちが「自分探しの旅」をする中で、心に響く出会いを促すためには、保育者は「豊かな文化」を用意し、子どもたちの興味や関心に気づき、想像力を働かせることが不可欠です。
具体的には、文化を「心を込めて取り組むこと」と捉え、子どもが「何かを作りたい」と思えるような環境を整えることが重要です。
例えば、積み木の数を増やすなど、子どもたちの創造性を刺激する工夫が挙げられます。
保育者は子どもの興味関心に注意深く「観察」し、彼らが何に喜びを感じるのかを把握することが重要です。
また、保育者が自ら楽しむ姿を見せることで、子どもたちの興味を誘い出すことができます。
子どもたちの創造性を刺激する環境作りのヒントは、私自身の表現活動にも活かせそうです。保育者が楽しむ姿を見せるという点も、とても共感しました。
子どもの権利条約と保育者の役割
子どもの権利、保育でどう活かす?汐見先生の重要ポイントは?
子ども主体の環境づくりと問いかけが重要!
保育現場における子どもの権利について、汐見稔幸先生の解説をご紹介します。
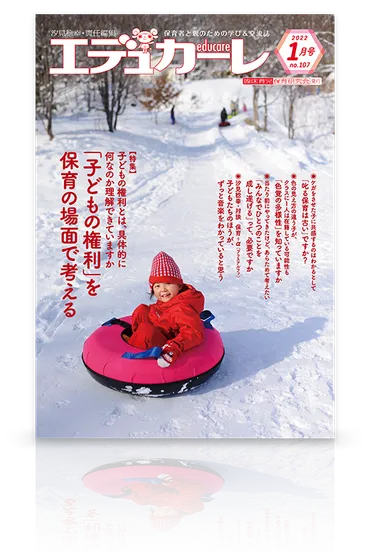
✅ 『エデュカーレ』2022年1月号(no.107)の特集は「子どもの権利」であり、保育の現場での考え方を提示している。
✅ 「叱る保育」や「みんなでひとつのことを成し遂げる」ことの必要性について再考し、色覚の多様性やSDGs教育など、現代的なテーマにも言及している。
✅ 汐見稔幸氏の対談や、保護者、職場、健康、環境など、保育に関わる様々な視点からの情報が掲載されており、保育者と親にとって学びと交流の場となる内容となっている。
さらに読む ⇒臨床育児・保育研究会出典/画像元: https://ikuji-hoiku.net/educare/no_107.html子どもの権利条約の背景や、保育現場での実践例について学ぶことができました。
子どもたちが主体的に考え、ルールを決定する環境作りの重要性を感じました。
保育現場における子どもの権利の具体化をテーマにしたセミナーで、汐見稔幸先生は、子どもの権利条約の背景、保育現場での実践、保育者へのメッセージについて解説しています。
条約の歴史的背景と基本方針を説明し、子どもたちが主体的に話し合い、ルールを決定する事例を紹介し、子どもの権利条約が子どもを「権利の主体」として捉えていることを強調しています。
保育者は、子どもたちが主体的に成長できるような環境を整えることが求められており、「あなたはどう思う?」「この時はどうしたらいいかな」といった問いかけを通して、子どもと一緒に考える役割が重要です。
汐見先生は、子どもの権利の本質、すなわち権利は当然として子どもが持つものであるという考えを示し、保育者への激励を送っています。
子どもの権利を尊重する保育の重要性を改めて認識しました。「あなたはどう思う?」という問いかけを通して、子どもたちと向き合いたいと思いました。
「ビビビ!」との出会い:保育者の導き
子どもの「やりたい!」を引き出すには?
文化との出会いを積極的に提供!
保育の質を向上させるために、子どもたちが「ビビビ!」と感じる文化との出会いをいかに提供するのか、汐見稔幸先生の考えをご紹介します。
公開日:2018/04/18

✅ 2018年4月に施行された保育関連3法令の改定は、保育の質を向上させるためのものであり、保育者一人ひとりが保育のあり方を考える機会となる。
✅ 保育の質とは、子どもたちの可能性を最大限に引き出すことであり、子どもたちの良い表情や自然な優しさ、温かさが見られるかを指標とすべきである。
✅ 子どもたちが本物の文化と出会い、深く理解する体験を通じて、その子の可能性を広げることが重要である。
さらに読む ⇒HoiClueほいくる|保育と遊びのプラットフォーム出典/画像元: https://hoiclue.jp/800008317.html子どもたちの可能性を引き出すためには、保育者が「ビビビ!」との出会いを積極的に提供することが重要ですね。
子どもたちの主体的な選択を尊重するという点が印象的です。
保育者は、誘導にならない範囲で、子どもたちが「ビビビとくる」ような文化との出会いを積極的に提供すべきです。
最終的に何に心惹かれるかは子ども自身が決めることであり、保育者はその選択を尊重すべきです。
保育士バンク!の連載企画第1回として、汐見稔幸教授へのインタビューがまとめられ、保育の質を向上させるための方法論が詳しく語られています。
子どもたちの「やりたい!」を引き出す環境作りは、AI社会で主体的に生き、物事を面白がる力へと繋がります。
子どもたちの「やりたい!」を引き出す環境作りの重要性を再確認しました。保育の質を向上させるための具体的な方法をもっと知りたいです。
AI時代を生き抜くために、保育を通して子どもたちの主体性や創造性を育むことの重要性を改めて認識しました。
💡 AI時代における保育の重要性と、子どもたちの主体性を育むための環境作りについて解説しました。
💡 子どもたちの「やりたい!」を引き出す声かけや、文化との出会いを促す保育の重要性について解説しました。
💡 子どもの権利を尊重し、主体性を育む保育のあり方について学びました。


