俵万智「蛇行する川」短歌とは?歌に込められた意味や表現技法を徹底解説!「蛇行する川には蛇行の理由あり」短歌の世界
人生の川は蛇行する。俵万智の短歌「蛇行する川には蛇行の理由あり 急げばいいってもんじゃないよと」は、焦らず本質を見つめる大切さを説く。蛇行する川の姿に、急ぎがちな現代人へのメッセージを込めた一首。日常会話を取り入れた言葉選びと、釧路湿原での体験が、人生という川の流れを鮮やかに表現。あなたの心にも、そっと語りかけてくるような、そんな歌です。
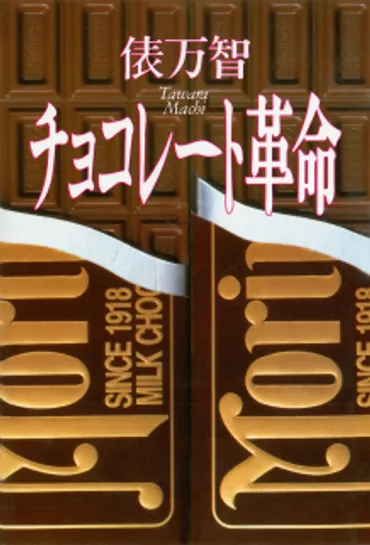
💡 俵万智の短歌「蛇行する川には蛇行の理由あり」は、人生や生き方を川の蛇行に例えた作品。
💡 短歌が収録されている歌集『チョコレート革命』や、作者である俵万智のプロフィールを紹介。
💡 短歌に用いられた表現技法や、短歌のテーマである人生観について解説します。
本日は、俵万智さんの短歌「蛇行する川には蛇行の理由あり」について、様々な角度から掘り下げていきます。
短歌の世界への入り口として、楽しんでいただければ幸いです。
始まりの歌、そして作者
人生の教訓を歌った俵万智の短歌、内容は?
急ぐだけが全てじゃない、という教訓。
まず、俵万智さんの短歌の世界へ足を踏み入れる前に、彼女の作品が収録されている歌集『チョコレート革命』についてご紹介します。
この歌集は、1997年に発表されました。
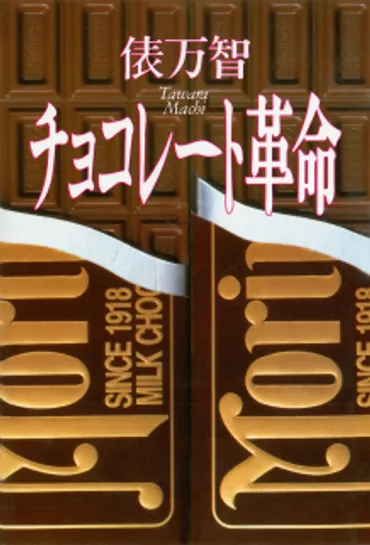
✅ 俵万智の第三歌集『チョコレート革命』の情報であり、1997年5月8日に発売された。
✅ 1987年の『サラダ記念日』ブームから10年後の、新しい愛の形を歌った歌集である。
✅ 内容は、愛と愛が戦うときの女性の変化に焦点を当てており、日本図書館協会選定図書に選ばれている。
さらに読む ⇒河出書房新社出典/画像元: https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309011332/『チョコレート革命』は、1987年の『サラダ記念日』から10年後の、新しい愛の形を歌った歌集とのことです。
短歌を通して、時代の変化を感じることができそうですね。
俵万智による短歌「蛇行する川には蛇行の理由あり 急げばいいってもんじゃないよと」は、歌集『チョコレート革命』に収録され、その歌は、蛇行する川の姿を通して、人生や生き方の比喩として、急ぐことだけが全てではないという教訓を伝えている。
作者である俵万智は、1962年生まれで、早稲田大学在学中から短歌を始め、現代短歌の第一人者として知られる。
彼女は『サラダ記念日』で社会現象を巻き起こし、口語短歌の先駆者としての地位を確立した。
この短歌は、まるで人生の教訓のようですね。焦らず、自分のペースで進むことの大切さを改めて感じました。もっと俵万智さんの他の作品も読んでみたいと思いました。
歌に込められた意味
人生の教訓!川の蛇行から何を学ぶ?
焦らず本質を見つめること。
次に、本題である短歌「蛇行する川には蛇行の理由あり 急げばいいってもんじゃないよと」に込められた意味を解説していきます。
この短歌は、どのような思いで詠まれたのでしょうか。
公開日:2022/07/31

✅ 俵万智の短歌「蛇行する川には蛇行の理由あり急げばいいってもんじゃないよと」は、蛇行する川を人生や生き方の比喩として表現し、急ぐことだけが良いわけではないというメッセージを込めている。
✅ この短歌は、第三歌集『チョコレート革命』に収録されており、釧路湿原の風景を詠んだ連作の一部で、釧路川の蛇行に着想を得ている。
✅ 表現技法として、反復法、話し言葉、擬人法、省略法、比喩(諷喩)、破調などが用いられており、特に「急げばいいってもんじゃないよ」という話し言葉が印象的である。
さらに読む ⇒あしかレビュー出典/画像元: https://asikareview.com/2022/07/tawara_dakou/この短歌は、人生を川の流れに例えている点が興味深いですね。
焦らずに、自分のペースで進むことの大切さを教えてくれるようです。
釧路湿原の風景からインスピレーションを得ているというのも素敵ですね。
この短歌は、蛇行する川が持つ「急ぐだけではいけない」というメッセージを語り手が受け止める様子を描いている。
蛇行する川にはそれなりの理由があり、急ぐことだけが全てではないという解釈ができる。
歌の核心は、焦らずに物事の本質を見つめることの大切さにある。
釧路湿原を訪れた際の体験に基づき、川の「蛇行」という言葉が、蛇が這うように曲がりくねっている様子を表し、人生の道のりを象徴している。
この短歌は、人生における様々な局面での振る舞い方を考えさせられますね。急ぐことばかりが大切ではないという視点は、これからの人生を歩む上で、心に留めておきたい教訓です。
次のページを読む ⇒
俵万智の短歌「急げばいいってもんじゃないよ」解説。釧路川の蛇行に人生を重ね、焦らず生きる大切さを表現。心に響く言葉選びと表現技法が魅力。

