科学技術史の視点?日本科学技術史の過去・現在・未来を紐解く科学技術史を俯瞰する〜科学技術立国としての日本の課題とは
科学史の奥深さを探求!入門1では、科学史の多様な魅力と固定観念を覆す視点を紹介。日本科学史では、トランスサイエンスをテーマに、科学技術と社会の接点を考察します。田口茂先生と共に、古代ギリシア哲学から現代の認知科学まで、科学の歴史的変遷を辿り、知的好奇心を刺激します。西洋と日本の科学観の違いや、技術と社会の相互作用から、科学技術の未来を読み解きましょう。

💡 科学技術史の多様性と面白さを伝える講義では、自身の興味関心を深めることができる。
💡 日本の科学技術史を題材に、科学への理解を深め、トランスサイエンスをテーマとする。
💡 科学技術立国としての日本の現状を分析し、改善策を見出す重要性を考察する。
それでは、科学技術史の世界へご案内いたします。
本日は、日本における科学技術の歴史、そしてその課題について、さまざまな視点から探っていきましょう。
科学史への誘いと日本科学技術史の視点
科学史入門1と日本科学史、一体どんな違いがあるの?
多様性と日本科学史、視点の違いに着目。
まず、法政大学の研究成果から、科学技術史の多様な研究領域をご紹介します。
経済学から女性起業家育成、日本の製薬企業の国際戦略まで、多岐にわたる研究内容を見ていきましょう。

✅ 法政大学イノベーション・マネジメント研究センターのウェブサイトに掲載されている研究業績が紹介されており、河村哲二氏、姜理惠氏、戸田江里子氏の研究内容と論文がまとめられています。
✅ 河村哲二氏は、グローバリゼーションやインフレーション、アメリカの労使関係など、経済学の幅広いテーマについて研究を行っています。
✅ 姜理惠氏は、女性起業家育成やファミリービジネス、起業家教育などに関する研究を行い、戸田江里子氏は、日本の製薬企業における国際戦略的提携について研究しています。
さらに読む ⇒法政大学イノベーション・マネジメント研究センター出典/画像元: https://riim.ws.hosei.ac.jp/research/journal.htmlこれらの研究は、科学技術史が多角的な視点を持つことを示唆していますね。
それぞれの専門分野が、時代や社会の動きと密接に結びついている点に興味を惹かれました。
科学史入門1では、科学史の多様性と面白さを伝え、受講者が自身の興味関心を見つけられるよう導きます。
事前の文献読解が必要な場合もあり、科学史に対する固定観念を覆すことを目指します。
一方、方法としての日本科学史は、日本の科学技術史を題材に、科学への理解を深めます。
特に、トランスサイエンスをテーマとし、科学技術と社会の接点における問題について考察します。
講師は田口茂先生で、哲学と科学の歴史的変遷、そして両者の融合について論じます。
科学史って、色んな分野と繋がってるんですね! 普段、興味あることと科学史をどう結びつけられるか、もっと深く考えてみたくなりました。
科学の変遷と「知る者」の視点
科学は「知る者」の問題をどう乗り越えた?
認知科学で「知ること」重視の流れ。
続いて、科学の変遷における「知る者」の視点に焦点を当てます。
保存修復の歴史を例に、科学的な知識と倫理観がどのように発展してきたのかを見ていきます。
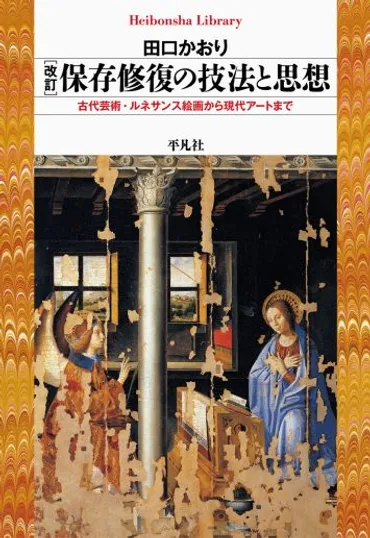
✅ 保存修復とは、作品の歴史を紐解き、傷や劣化に対して修復の必要性や方法を検討する行為であり、「最小限の介入」という考え方が重要視されている。
✅ 保存修復の歴史は、1966年のフィレンツェ大洪水で技術が向上し、1800年代からの「つくる」と「なおす」の区別、専門家の育成が進んだことで大きな転換期を迎えた。
✅ 現代の保存修復では「可逆性」と「適合性」を重視し、修復が作品に与える影響を考慮し、必要以上の介入は避けるという倫理観が重要視されている。
さらに読む ⇒ほとんど0円大学|おとなも大学を使っちゃおう出典/画像元: https://hotozero.com/knowledge/kyotouniv_conservator/保存修復における「最小限の介入」という考え方に、非常に共感しました。
科学的な知識と倫理観のバランスが、持続可能な社会を築く上で重要だと感じます。
田口先生の講義は、古代ギリシア哲学から始まり、合理性と秩序を追求する姿勢が科学に受け継がれた様子を辿ります。
17世紀の科学革命を経て、近代的科学は客観的な知識を追求しましたが、20世紀に入り、相対性理論や量子論の登場によって、科学は再び「知る者」の問題に直面しました。
近年では、認知科学の発展により、「知ること」が重視されるようになり、科学に新たな潮流が生まれています。
科学の進歩は、人間の「知りたい」という欲求から生まれるのですね。固定観念にとらわれず、様々な視点から物事を捉えることの大切さを改めて感じました。
次のページを読む ⇒
科学技術史から学ぶ3つの教訓! 欧州の原理追求、道具への技巧、技術の連続性。日本との対比から、科学技術発展の秘訣を読み解く。

